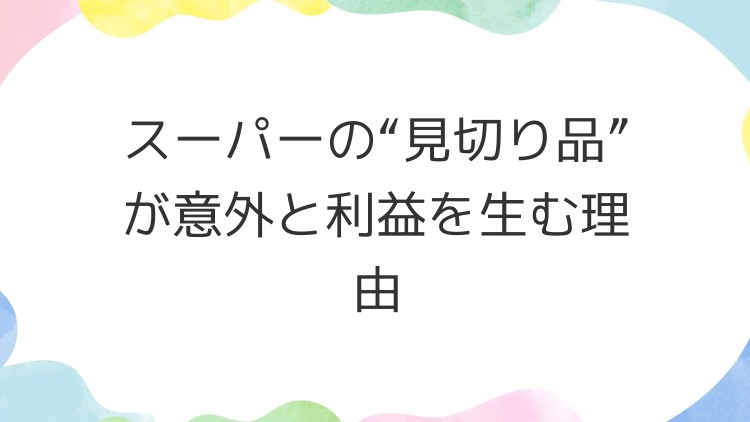なぜスーパーは「安売り」で儲かるのか

スーパーの店内を歩いていると、値引きシールが貼られた商品をよく目にします。
一般的には「値引き=損失」というイメージがありますが、実はこの「見切り販売」こそがスーパーの利益を支える重要な戦略なのです。
鮮度が落ちた商品を廃棄すれば原価分がまるまる損失になりますが、原価を少しでも回収できれば、その分だけ損失を減らせます。
例えば498円の惣菜が半額の249円になっても、原価が150円なら99円の利益が出ます。
さらに重要なのは、見切り品を求めて来店した顧客が他の定価商品も購入する「ついで買い効果」です。
データによれば、見切り品目当てで来店した客の約70%が予定外の商品を1品以上購入するといわれています。
つまり見切り品は「集客装置」として機能し、店舗全体の売上向上に貢献しているのです。
「賞味期限間近」が回転率を高める仕組み
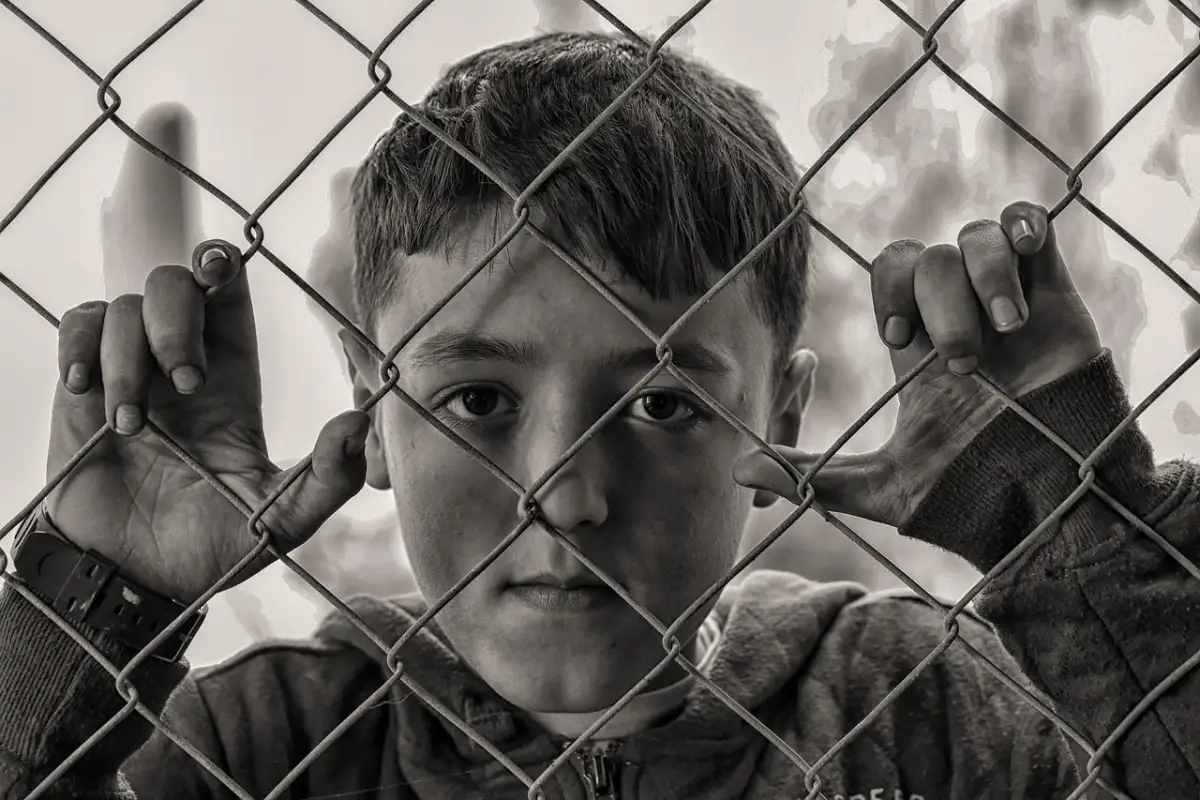
スーパーマーケットにとって商品の「回転率」は利益に直結する重要な指標です。
見切り品の設定は、この回転率を高める効果的な手段となっています。
賞味期限が近づいた商品を値引きすることで、通常なら廃棄される運命だった商品に「今買うべき理由」を付加し、購買意欲を刺激します。
これにより商品棚の新陳代謝が促進され、常に新鮮な品揃えを維持できるのです。
実際、適切な見切り販売を実施しているスーパーでは、生鮮食品の廃棄率が平均10%以上低下するというデータもあります。
また、見切り品コーナーは「宝探し」的な楽しさを提供するため、顧客の来店頻度を高める効果もあります。
多くの消費者が「お得な掘り出し物を見つけるため」に週に複数回来店するようになり、結果として客単価の向上にもつながっています。
見切り品は単なる「売れ残り処分」ではなく、計画的な在庫管理と顧客心理を巧みに活用した経営戦略なのです。
消費者心理を刺激する「限定感」の威力

見切り品に貼られた赤い値引きシールには、消費者の購買意欲を強く刺激する心理的効果があります。
「今だけ」「ここだけ」という限定感は、人間の損失回避本能に直接働きかけるのです。
行動経済学では「希少性の法則」として知られるこの現象は、通常なら必要としない商品でも、限られた機会にしか手に入らないと分かると欲しくなる心理を指します。
見切り品はまさにこの原則を体現しています。
数量限定で、明日には無くなっている可能性が高いからこそ、「今買わなければ」という切迫感が生まれるのです。
また値引き前の価格が明示されていることで、消費者は「得をした」という満足感も得られます。
これは「アンカリング効果」と呼ばれる心理現象で、最初に示された価格を基準に値引き後の価格を割安に感じる仕組みです。
こうした複数の心理的要因が重なり、見切り品は単なる値引き商品以上の魅力を持ち、結果的に廃棄ロスの削減と売上増加という二重の利益をスーパーにもたらしています。
食品ロス削減と経営効率が両立する好循環

見切り品販売は、スーパーの利益向上だけでなく、社会問題である食品ロス削減にも大きく貢献しています。
日本では年間約612万トンの食品ロスが発生しており、その約半分は流通・小売段階で生じています。
見切り販売を積極的に行うスーパーでは、廃棄率が従来の3分の1以下になったという事例も少なくありません。
この取り組みは単なるコスト削減策ではなく、環境負荷低減という社会的価値も生み出しているのです。
また、計画的な見切り販売は在庫管理の精度向上にもつながります。
どの商品がいつ値引きされるかデータを蓄積・分析することで、より効率的な発注や陳列が可能になり、経営の全体最適化が進みます。
さらに近年では「食品ロス削減に貢献している」という企業イメージの向上効果も見逃せません。
環境や社会問題に関心の高い消費者からの支持を集め、顧客ロイヤリティ向上にも寄与しているのです。
見切り品販売は、経済合理性と社会的責任を両立させる現代小売業の理想形といえるでしょう。
まとめ
スーパーの見切り品販売は、一見すると利益を削る行為に思えますが、実は廃棄ロス削減、回転率向上、集客力アップ、ついで買い促進など多面的な効果をもたらします。
消費者の「限定品」への心理的反応を利用しながら、食品ロス削減という社会的課題にも対応する、現代小売業の合理的な経営戦略といえるでしょう。